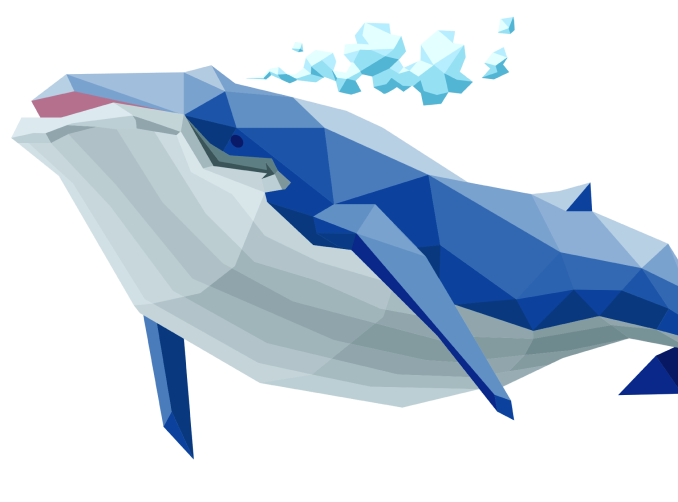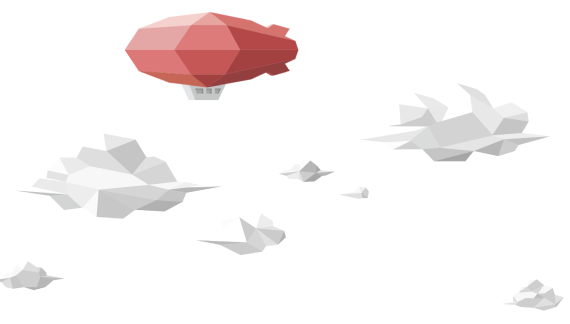【ユーザーインタビュー】千葉リハビリテーションセンター 様
デジリハって実際どんな施設で、どんな風に使われているんだろう?
そんな疑問の声にお応えして、デジリハユーザーを紹介していきます!
今回紹介するのは、千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーション治療部 小児療法室作業療法科 科長の三屋先生です。
デジリハを導入してから約2年の月日がたちます。導入当時の使い方やセラピスト同士の変化や、病院だからこそデジタルを活用できる面を伺ってきました。
ーーデジリハを導入して2年が経ちますね。導入のきっかけを覚えていますでしょうか?
2022年からデジリハを活用しています。思い返すと、2026年のセンター建て替えに向けた備品や設備の見直しに、デジリハを導入してみたいという声がスタッフから上がってきて、「これは面白そうだ」と感じ、建て替えを待たずに前倒ししてデジリハを導入することになりました。
ーー三屋先生の経歴について教えてください。
作業療法士になって19年目になります。6年間総合病院で回復期から生活期まで、脳血管障害や整形疾患、内部障害などを経験してきました。子どもが生まれたことをきっかけに、発達障害領域の作業療法や特別支援教育の分野に興味をもち、総合病院を退職後は、千葉県千葉リハビリテーションセンターで脳性麻痺などによる肢体不自由児や重症心身障害児者への作業療法を担当しています。2男1女の父親としても、公私ともに子どもたちに囲まれた毎日を送っています。
ーー千葉リハビリテーションセンターについてもう少し特徴を教えていただけますでしょうか。
当センターは医療と福祉が複合した 千葉県で唯一の総合リハビリテーションセンターなんです。乳幼児から高齢者まで、医療だけでなく福祉を利用した社会復帰に至るまで、包括的なリハビリテーションを提供しています。地域支援センターは千葉県の高次脳機能障害支援の拠点機関、総合療育センターには愛育園、児童発達支援センター、千葉県医療的ケア児童支援センター(ぽらりす)など、県内の脳性麻痺児、肢体不自由児、重症心身障害児者など障害を持った方に対して、入園、通園、短期入所、相談支援も行っています。どんなに重い障害があっても、地域社会の一員として、健康で文化的な生活が送れるよう、医療・福祉・教育機関と連携しながら、療育サービスを包括的に提供しているのが特徴です。
ーー三屋先生が率いるチームはどのようなスタッフで構成されていますでしょうか。
新人から20年目以上のベテランスタッフが揃っており、リハビリテーション治療部には療法士が123名います。その中でも小児を担当する作業療法士は12名、理学療法士は18名です。小児療法室があり、ここでデジリハを使っています。入院や外来でいらっしゃるお子さんが多く、県内でも数少ない最新のリハビリ機器も多数導入しています。

デジリハを外来でのリハビリテーションや入院の施設内で日々活用しています。
ーーデジリハを導入して約2年が経つと思いますが、デジリハを導入した当時のことは覚えていたりしますか?
正直いうと、導入時はすぐには活用できていなかったんです。単純に新しいものを導入するので、使い方がわからない、センター内でも広まらない。初めは、外来担当の理学療法士や入園担当の作業療法士など、小児担当の各科から代表セラピストを一人ずつ集めて「デジリハLab(デジリハラボ)」という名の精鋭チームを結成し、チーム内で使い方をレクチャーしたり活用方法について定期的にミーティングをしたりしました。実際に現場でちゃんと使ってもらうまでに、2〜3ヶ月くらい時間がかかったと思います。
このチームは1年間限定のチームだったのですが、最後に実施件数やデジリハを活用した報告会も実施しました。最初はどうなるかな?と不安に思っていた時もあったのですが、超ベテランのチームメンバーがリハビリツールとしてたくさんのお子さんに活用していて、一番使いこなして、たくさんの報告をしてくれたのがすごく嬉しかったです。子どもたちにとって最善で楽しいツールを見極めて、すぐに使いこなすことができるベテランセラピストの背中を見せてもらうこともできて、やっぱり先輩はすごいなと素直に感じました。
ーーデジリハを活用してみての何か気付きや発見はありますか?
最初はこんな楽しいリハビリ機器があることに驚き、興味を持って体験したがるお子さんが多かったです。一度やってみると、「次も遊びたい」「触りたい」と前のめりになるお子さんが増えたと思います。リハビリで機嫌を悪くして泣いてしまう子もいて、モチベーションが低いお子さんには、デジリハから開始してリハビリに取り組んでもらうような流れにすることもあります。今までの不機嫌が嘘のように、表情が180度変わり、気持ちが切り替わって遊び始めるので、心の変化が目に見えてわかるんです。
ハマる子にはすごくはまっているんです。セラピストがこんな動きをしてもらいたいという動きをしてくれるんですよね。タッチする指や腕の動作やアニメーションを見ながら横に動いて、触ったり。ジャンプしたり。
「そらの水族館」はみんなのリアクションがとてもいいです。オブジェクトのレイアウトを変えて、車が好きな子には車だけ出したり、背景を黒にしたりして、その子に合わせてカスタマイズできるので、すごく集中して取り組んでくれます。「忍者でドロン」は“戦う”要素もあって、特に男の子は熱中するんです。
集中できない時とか、機嫌を損ねちゃった時には「じゃあデジリハやってみる?」と声掛けすると、さっきまでの様子が嘘のように興味津々の表情になったりして。デジリハの部屋に入って、画面が切り替わると、気持ちも切り替わって、表情も変わるんです。

変化の観点でいうと、やはりチーム「デジリハLab」を結成したことがよかったと思います。セラピスト間同士のコミュニケーションは今まで以上に増えたと思います。デジリハを導入することによって、各科との繋がりがさらに広がったと感じています。「⚪︎⚪︎君にはどんな使い方がいいだろう?」とか「〇〇さん、デジリハやったら膝歩きしたんだよ!」「忍者を一生懸命やっつけている間ずっとバランスよく立っていたよ!」みたいな会話をたくさん聞くようになったので、これもこのツールが生み出した大きな変化だなと感じました。
ーーリハビリ病院でデジリハを活用する強みはありますか?
医療機関で子どもにリハビリを提供するにあたって、発達支援という重要な役割があります。寝返りやお座り、ハイハイ、膝立ち、つかまり立ち、横歩き、伝い歩きなどの身体や手の使い方となどなど。単純にその動きを誘導することもありますが、それだけだと子どもからすると ”やらされている”感覚になると思うんです。だから泣いてしまったり、ぐずってしまったり、怖い思いをしたりすることもあるかもしれません。リハビリでやってもらいたい動きがネガティブな印象を抱かせてしまうこともあるんですよね。やっぱり、お子さんたちが色々な遊びを通して、主体的な身体の動きを促せる、導き出していけることが理想だと思っています。そういう意味でもデジリハは、子どもの興味を引き出し、遊びの中で“自然に”自発的な動きがでてきます。そこに本人の意思が働き、興味が広がって、「できた!うれしい!たのしい!」が増えるきっかけに繋がっているなと感じました。
「身体が動けば心も動く、心が動けば身体が動く」

「身体が動けば心も動く、心が動けば身体が動く」これは私たちが大切にしている視点で、デジリハを活用して遊んでいるお子さんは、心も身体も主体的に動いていることがわかります。
普段リハビリを通して、家族やきょうだいと一緒に遊ぶことってそんなに多くないと思うんです。でもデジリハは、一緒に外来について来てくれたり、お見舞いにきた家族やきょうだいが一緒に遊べるんですよね。しかも自然発生的に。関わる人との気持ちを共有し、嬉しい、楽しいという共感を生むきっかけになっている気がします。入院しているお子さん同士が複数で一緒に使ったりもしますが、関係性を深めるきっかけとか、社会性の発育にも繋がっていくものなのかなと思いますね。
もうひとつ私たちが大切にしている視点で、”6F-Words”というワードがあります。これはいわゆるICFの子ども版のようなもので、その一つに個人因子に当たる「FUN」つまり「楽しむこと」の重要性があります。
どれも子どもたちにとって大切なもので特に優先順位はありませんが、Function(機能) Family(家族) Fitness(健康) Fun(楽しみ) Friends(友情) Future(未来)などの頭文字に”F”がついた言葉です。
デジリハは、リハビリにゲーム要素を取り入れて、ゲーム感覚で身体を動かしながらリハビリが提供できるツールです。まさにデジリハに触れているときは、”患者”ではなく”プレイヤー”になっていて、いつのまにか楽しみながら心と身体を動かせる状態になっていると感じます。
ーーリハビリテーション病院でデジリハを日々活用している三屋先生から、最後にメッセージをお願いします!
リハビリテーション病院の特徴や入院、通院している患者さんは様々だと思いますが、デジリハを使うことで、リハビリを提供する側の視点でも違った見方ができ新しい発見があると思っています。
僕が肌で感じているのは、間違いなく近年リハビリテーション医療においてもDX化の波がきているということ。数年後には専用品ではない、汎用性の高いデジタル機器などの道具がリハビリテーションにおいても当たり前に現場で活用される時代がすぐそこまできている。そういう観点からも、デジリハは細かな道具を用意して毎回調整する手間や労力が圧倒的に少ないので、年齢、性別、障害があるなしに関係なく“どんなお子さんも同じスタートラインにたって遊ぶことができる”ひとつの重要なツールになっていると思いますし、そういった時代がすでに来ているのだと思います。お子さんたちにはもちろんですが、最新のデジタルリハビリテーションツールとしてデジリハを活用してみてはいかがでしょうか。是非たくさんの活用のアイディアを療法士のみなさんと共有していきたいです!
“子どもたちのFUNに彩りと広がりを!”
デジリハは、子どもたちのFUN(できた!うれしい!たのしい!)をたくさん彩ることのできるツールだと思っています!子どもたちのFUNがデジリハを通じてもっと広がってほしい!デジリハとともに子どもたちとその家族の笑顔が日本に、世界に咲き誇っていくと嬉しいですね。

ウェブサイト:https://www.chiba-reha.jp/
x:https://x.com/chibareha
Instagram:https://www.instagram.com/chibareha/
更新日:2025年2月12日
記事一覧に戻る