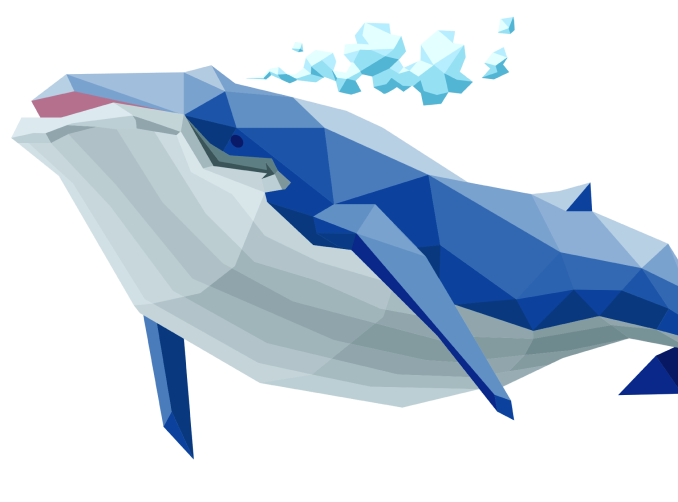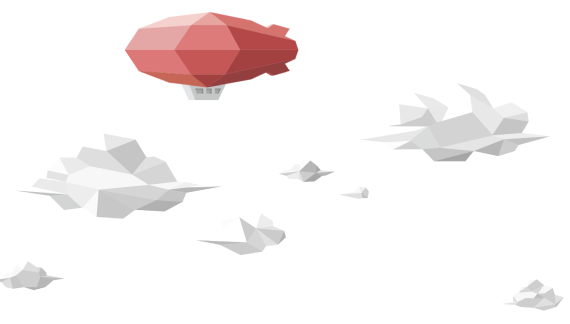【ユーザーインタビュー】放課後等デイサービスkukuna 様
デジリハって実際どんな施設で、どんな風に使われているんだろう? そんな疑問の声にお応えして、デジリハユーザーを紹介していきます! 今回は沖縄県重症心身障害児デイサービスを展開する kukuna代表の上地さんにオンラインでお話を伺いました。デジリハの存在を知ってから、問い合わせ〜導入まで1週間というスピードで前のめりで活用いただいています。
上地 幹大
大学時に教員免許(保健体育)を取得し、大学卒業後は沖縄県の特別支援学校に勤務。 その後、重心特化型の児童デイサービスへ入職し、令和6年4月にkukunaを立ち上げ、現在に至る。
ーーデジリハの導入のきっかけについて教えてください
デジリハを知った経緯は同業種の知り合いから教えてもらいました。以前沖縄でデジリハの体験会があり、その知り合いが体験会に参加したとのことで、お話を聞いてからすぐにウェブサイトやInstagramでデジリハのことを調べました。kukunaを開設する前から、身体を動かせるプログラムを取り入れたいと考えていたので、「今だ!」と前のめりで動き、問い合わせから導入まで1週間くらいだったと思いますね。
kukunaの施設の特徴は…実は一軒家!
重心障害児や医療的ケアが必要なお子さんが通ってくれています。施設自体が小規模で1日の利用者は5名程度。専門職は児童と同じくらいの人数の配置で、基本的にはマンツーマンで手厚く一人ひとりにあった支援を提供しています。理学療法士、作業療法士、看護師もいるので医療的ケアが必要なお子さんでも安心して通うことが可能です。
施設の特徴としては、ここkukunaの施設、実は一軒家なんです!
ワンフロアで広々とした施設も療育に適していると思うのですが、僕たちは子どもたちが”安心して通ってくれる”ことを大切にしたくて、環境や居場所づくりも意識しました。イメージとしては”第二のお家”ですね。
リビングや畳、キッチンがあるので、まるで家にいるかのようにリラックスできると思っています。見学にきたご家族さんや関係者の方も、「お家みたい」と言ってくれるんです。
またkukunaは住宅地にあり、実は施設の看板を出していません。看板出しちゃうと”施設”っぽさが出ちゃうと思い、あえて出していないんです。
子どもたちには”楽しんでもらう”ことも意識して、のんびりイキイキ過ごせる場所を作っています。そのためには安心感を与えて楽しんでもらえる施設を目指しています。
ーーお家のような場所だったら、必然的に通いたくなりますよね。
子どもたちを”楽しませたい”という想いがあるので、同じ空間にいるだけでセラピストも気分が上がりますし、一緒に過ごしていて楽しいですよね。玄関の扉を開けたら思わず、「ただいま!」って言っちゃうくらい、アットホームさはあると自信もって言えます。バリアフリーも完備していて段差がない分、思い切って動き回れるのも大きいと思います。
ーー楽しく安心して過ごせる環境づくりというのは、上地さんの過去の経験があるのでしょうか?
kukunaを立ち上げる前は事業所で働いていました。そこの施設も似たような一軒家だったんです。当時は珍しくて、空間が違うだけでこんなにリラックスできることが居心地良くて。お家だったら、”通う”じゃなくて、”ただいま”と言っちゃう空間になるだろうから、きっと同じ空間にいるだけで楽しいだろうなと、そのときからひっそり思い描いていました。
ーーkukunaではご家族とのコミュニケーションの一つにデジタルの連絡帳を取り入れているようですね。
kukunaではデジタル連絡帳を活用しています。ひと昔前の連絡帳でいうと文字を書くだけだったと思うんですが、文字だけでは伝わらない部分は写真や動画を添付して共有しています。やはりビジュアルで伝えることはお母さんお父さんたちに安心感を与えられていると感じています。
例えば、外の活動だと、「今日⚫︎⚫︎くんが公園でブランコに初めて乗りました!楽しそうでした」と伝えても、どう楽しんだのか、喜んでいたのか伝わらない。お子さんの愛くるしい笑顔や嬉しそうな表情を一瞬一瞬切り取り共有しています。
もちろん、デジリハを活用して遊んでいる写真や動画はバンバン載せて共有しています!
デジリハを初めて知るご家族さんは「なにそれ!」「面白そう!」「今度見に行っていいですか?」とポジティブな反応が返ってきます。デジリハを活用しているお子さんの表情や動きを見て、楽しそうというのが伝わるんだと思います。
ーー現在はmoffバンドを導入してくださっていますね。お子さんに人気のアプリはありますか?
moffバンドは腕や足に巻きつけて運動ができる点はすごく魅力的ですよね。身体機能の向上に役立っていると思います。
児童とセラピストに人気なのが、「お坊さんにいたずら!」。お坊さんが振り向いた姿と怒っている表情が面白くて(笑)。あるお子さんは、お坊さんが振り向いたときに見せる「?」の表情が好きなんですよ。視覚障害の症状があるお子さんもいるんですが、バンドを振ったら、「ひゅーんっぽんっ!」の効果音に反応して爆笑してくれるんです。それにつられてセラピストたちも笑ってしまう。ゲームで遊ぶ→子どもが面白がって笑ってくれる→セラピストもつられて笑う。ポジティブな循環が生まれて施設の雰囲気がとてもにぎやかになりました。まるで家族と過ごしているみたいです。
あとは「びしゃびしゃパニック」も人気ですね。バンドを振ると水が発射されて、中心にいた人たちが散らばっていく。お子さんが遊んでいるときにたまたまお母さんが横にいて、
「しっかりゲームのこと認識しています」と教えてくれて、お母さんにもお子さんの変化を知ってもらえた瞬間だと感じました。
ーー初めてデジリハに向き合うお子さんの反応はどんな感じでしたか?
はじめはどうやって遊ぶものかをわかっていなかったです。セラピストと二人三脚で「こうやって動かすとね、水が出るんだよ」とか「お坊さんにこんな感じでバナナを投げてみてね」と声かけしながら教えました。つきっきりで教えていくうちに、ゲーム性を認識し始めてくれました。僕たちセラピストも当初は子どもたちが理解してくれているのか不安でしたね。そんなときは、お子さんのことを一番理解しているご家族とコミュニケーションを図り、遊んでいる動画を見せてあげながら、「今日はこんな感じで一緒に遊んでみたんですが、⚫⚫ちゃんの動きや様子はどうでしょうか?」と動きを一緒に確認していきました。
導入して1ヶ月ちょっとなので、まだまだこれが正解なのか分からないことだらけ。ゲームの意味を理解してもらうというのは時間がかかるものです。単純にゲームだけをさせておくだけでは、飽きちゃったり、意味がよくわからないまま終わっちゃったりもします。セラピストやスタッフが家族と会話を重ねていくことで、少しずつ変化していくものだと思っています。
ーーデジリハの活用頻度についてはいかがでしょうか?
学校が終わって、kukunaに”帰ってくる”時間が大体午後になるので、最長で活用して1時間くらいですね。重心のお子さんはケアや吸引があったり、お風呂に入れる時間もあるので、毎週毎日この時間を使うことは決めていなくて。5分でも時間ができたら、一緒に遊ぶようにしています。日々の積み重ねだと思うんです。
ーーmoffバンドを活用している上で、苦労したことやこんなふうに工夫したことはありますか?
moffバンドを腕につけてゆっくり動かしながら遊んでいたんですが、設定で感度調整しても反応しなかったことがありました。その子なりに一生懸命バンドを振っていたので、どうにか反応させてあげられないか…と一時悩んだことがあったんです。タイミング良くデジリハ代表の岡さんが施設に遊びにきてくれて、そのことを相談してみたら「紐にmoffバンドを通し吊り下げて見てはどう?」*という提案があり、チャレンジしてみたら、これで試してみたらちょっと触っただけでゲームが反応して、新しい発見でした。
*moffバンドのバンド部分は取り外しが可能です。
他のお子さんですと、ゆっくりmoffバンドを動かすお子さんがいます。タッチするまでの時間は30分。僕らは地蔵のようにタッチするのをじっくり待っています。
もちろんご家族に「タッチさせるにはどうしたらいいでしょうか?」と相談することもありました。「少し時間がかかる子だから待たせてあげてほしい」という希望だったので、期待に添えるよう支援してきました。
ーー上地さんが療育で大切にしている考え方について教えてください。
障害の種類や疾患によって、自身の感情をコントロールしたり表現できなかったりしますよね。ご家族がそこを一番理解しているのでしっかりお話を聞くようにしています。お子さんの様子の共有の仕方も、メールやテキストだけの一方的な連絡ではなく、写真や動画で共有と相談します。「もしかするとこんな動きは苦手なのかも?」と気付きや発見を伝えると、家族がこれまで知らなかったお子さんの新たな一面の発見に繋がって、「うちの子そんな表情するんだ!」と驚かれることもあります。
いくらレベルの高い療育やリハビリをさせても、子どもたちが「楽しい!」と心の底から感じてもらえないと、モチベーションには繋がらない。明るく楽しい声掛けも意識していますね。子どもは褒められると伸びる。どんどん褒めていっぱい声掛けをする。そうするとスタッフの表情もにこやかになって雰囲気がぱっと明るくなっていく。とてもシンプルなんですが、僕の考え方は「楽しくやっていきたい」の一言に尽きます。
ーーデジリハを導入してからの変化は何かありますか?
デジリハを導入してからは、スタッフ間のコミュニケーションが活発になりましたね。例えば、「どのゲームがどの子に合っているかなぁ」「楽しんでもらえているかな」とお互いに質問しあっています。変化という部分では、遊んでいる姿を広めたいので、Instagramでデジリハを発信することが増えました。ユーザーさんから「これ何ですか?」と質問が結構増えました。
ーー沖縄では”初”の放課後等デイサービスの導入になりました。これからデジリハを活用していく意気込みをお願いします!
デジリハを通じて、子どもたちが楽しく成長できる環境をさらに充実させていきます。活用や工夫を取り入れながら、地域のモデルケースになれるよう目指していきたいですね。また保護者や地域の方、教育機関等も連携を深めていくことも考えています。デジリハACADEMTYの参加も楽しみですし、たくさん吸収して子どもたちの可能性をひろげていきたいです!どうぞよろしくお願いします!
kukuna:https://www.kukuna-okinawa.com/
instagram:https://www.instagram.com/kukuna.2024/
掲載日2025年2月4日
記事一覧に戻る