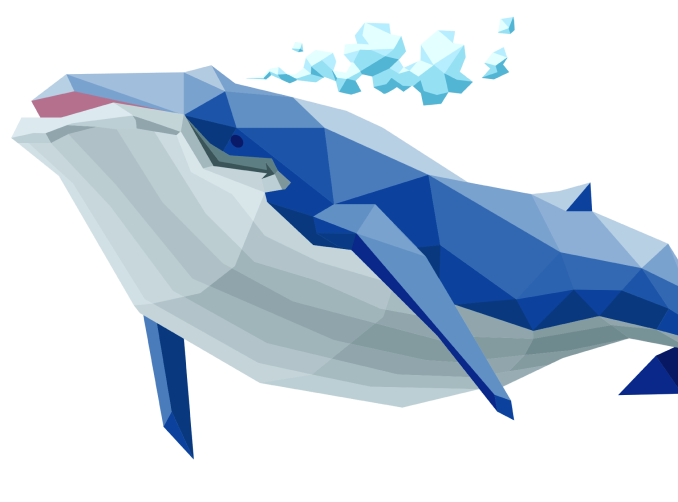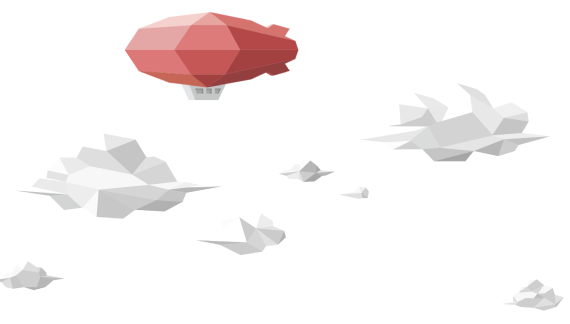【ユーザーインタビュー】八尾市立障害者総合福祉センター 様
デジリハって実際どんな施設で、どんな風に使われているんだろう? そんな疑問の声にお応えして、デジリハユーザーを紹介していきます!今回は八尾市立障害者総合福祉センターで、児童発達支援管理責任者として勤めていらっしゃる水野さんに、デジリハを導入したきっかけや使っていく中で見えてきた変化や感想を伺いました!
ーーまずは水野さんが勤めていらっしゃる八尾市立障害者総合福祉センターについて簡単に教えてください。
当施設は児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、高齢通所介護と子どもから高齢者までが通うデイサービスの場です。特に児童発達支援、放課後等デイサービスは主に医療ケア児、重症心身障害児を優先的に受け入れています。毎日、50名近くの利用者がおり、子どもであれば遊びや生活を通して発達支援を行い、成人であれば、生活面での介護に加え、余暇活動や全体でのレクレーションなどを実施し、より良い生活が送れるように取り組んでいます。幅広い年齢層の利用者がおり、世代交流ができるといったところも施設の特徴です。その他、施設内には料理、茶道、カラオケルームにスポーツジムもあり、外部団体への貸し出しもしています。障害のある方を対象にパソコン教室や手話講座、陶芸教室などの各種講座も開催しています。
ーーデジリハを利用いただきありがとうございます。約9ヶ月ほど活用してみていかがでしょうか。
デジリハのツールに対して子どもたちの食いつきがすごいです。普段からデジタルに慣れている世代なので、ぱっとスクリーンに触れる子たちも多いです。子どもたちだけではなく、私たち支援員も一緒に遊んでいく中で、介入していけることも大きなポイントだなと思っています。
画面へのタッチの仕方やボールの転がし方の工夫は、デジリハ営業の森原さんからアドバイスをいただき参考にしました。子どもたちにとって興味関心を広げるツールになっていると遊ぶ姿をみていて感じています。
ーーそもそものデジリハを知ったきっかけについて教えてください。
約2年前にホスピタル・プレイ・スペシャリストの資格を取りたく、静岡県立大学が開講している講座に申し込もうとした時に、シンポジウムでデジリハの紹介がありそこで知りました。
ホスピタルプレイスペシャリストとは遊びを用いて医療環境をチャイルドフレンドリーなものにし、子どもたちが医療経験を肯定的に捉えるようにするため小児医療チームの一員として働く専門職のこと
ーーなぜ…ホスピタル・プレイ・リストに興味を持ったのでしょうか?
前職で働いていた施設で、この資格を持っているスタッフがたくさんいて。総合的な施設だったので、例えば子どもたちがインフルエンザや病気の処置が必要な場合、資格を持ったスタッフが、子どもたちに遊びながら対応していました。その施設を出た時に、今の職場で彼らのように対応するスタッフや環境がなかったので、この機会に取ってみたいと思ったのがきっかけです。ちょうどコロナ禍のタイミングでオンライン講座ができたことも、受講してみるきっかけになりました。
ーー初めてデジリハを知って使ってみた時の印象はどうでしたか?
「デジタルを保育に使うのはどうなの!?」と少し驚くスタッフもいました。しかしデジタルは遊びのツールとして、子どもたちにとっては分かりやすいものだなと観ていて思います。動いている絵を目で見ても楽しい、音も聞こえてくる、自分が起こした行動によって反応が即時に返ってくることは、やっぱり分かりりやすい。だからデジリハは活用していきたい思いましたね。
ーーありがとうございます! 実際デジリハを約9ヶ月ほど活用してみての、そこからの印象はどうでしょうか?
まず、体験の初日は…「すごい!!」の一言でした(笑)。スクリーンに映像を映すと、子どもたちが集まってきて。私から遊び方は教えていなくても、理解できる子はすぐに遊んでいましたね。背後でパソコンを操作しているデジリハ岡さんを見ては、「次は何?」と関心を示してくれて、ゲームに入り込んでいく姿を見ると、子どもって大人が思っている以上に力があると実感しました。デジリハを使い続けてきて、子どもたちが変わってきているなと感じますね。
ーー子どもたちの変わり方という点では、変化はどんなところにあります?
はじめは「手を合わせてパチパチしてね」と教えても、楽しくリズムを刻んでくれたり真似をしてくれても、スクリーンとは別のところをみてることがありました。
最近は宝石が降ってくるゲームで”しゃらしゃら〜”と音が鳴ると、スクリーンに目を向けて、反応しているんです。自分の行動がスクリーンに映る、行動と反応が繋がっていることを理解していると感じました。私がスクリーンの前に立って、「宝石をキャッチするから、星を降らせてね!」と伝えると、スクリーンに星を降らせてくれて、楽しんでもらえます。デジリハはコミュニケーションツールだと思います。
ーー使っている場所や頻度はどれくらいになるのでしょう?
日中のメインの活動が始まる前の待ち時間に触ってもらったりしますね。朝きてくれた子どもたちから順番に遊んでもらっています。頻度でいうと、だいたい週1〜2回触ってもらっています。
デジリハで遊んでもらう場所は、うちの施設ですとオープンスペースで対応することが導入条件で、大人の利用者も通るスペースで遊んでいます。通りがかりの大人たちから「お!今日も遊んでるね!」「頑張って〜!」と声をかける人も見かけますよ。
ーー人の目につくという観点では大人にも興味を持ってもらえますね。実際にデジリハを操作したり、一緒に遊んでくれたりするスタッフですと、どのような職種の方がいらっしゃるのでしょうか?
看護師、OT・PTのセラピストの先生、放課後等デイサービスの先生も入ってくれたりします。
ーー他のスタッフさんからの反応はどうですか?
年齢層の高い介護職のスタッフもいらっしゃるので、デジタルに慣れていない方ですと、デジリハを操作することに怖いイメージを抱く方もいらっしゃいます。ちょうどデジリハを利用している他の施設で「忍者でドロン!」をしていることを耳にしたので、私たちの施設でも3日間「忍者ゲーム大会」を開催したんです(笑)。そしたら大盛り上がりで! 職員や大人の利用者さんも交えて、15体の忍者を何秒で倒せるか、時間で競いましたね。実際の設定は、独歩や車椅子の人などに合わせて調整しました。
高齢の利用者さんは初めは遠慮していたのですが、いざやってみると本気で遊んでいて、子どもたちの1位をかっさらっていく勢いで(笑)。
3日間で職員からスタッフ、利用者、そして運転手も含めて、40〜50名ほど集まりましたね。
ーーこのような大会をきっかけに、高齢者介護でもやってみようと増えたりしたら嬉しいですね。
はい、スタッフからも実際に遊んでいる場面をみてくれていて、判断して動くという観点で「脳のトレーニングにもなるから高齢の方にもいいかも」とおっしゃってもらいました。ゲーム性を取り入れてみんなで遊ぶことができるのもデジリハならではだと思いました。
ーー今後デジリハをこんなふうに使っていきたい希望はありますか?
子どもだけで使って終わらせることはもったいないので、高齢の方にも広く使ってもらいたいです。またデジリハを使ったリハビリの効果や証明も必要だと思っています。
ーーよく私たちが耳にするのはリハビリスタッフがいないから、デジリハは導入難しいかもしれないです…大丈夫ですか?と質問を受けることもあり、主体的にデジリハを引っ張っている水野さんから一言メッセージをお願いします!
私の考え方としては、「リハビリ」ではなく「遊び」だと思い取り掛かっています。子どもたちが自然に遊んでいる姿を微笑ましく見ています。リハビリをさせているわけでもなく、でも単に遊ばせているわけでもない。デジリハだから大人も子どもも一緒に、わいわい明るい空気感が溢れていると感じています。
医療でいうとリハビリしたことで「歩けるようになった」「立てるようになった」等と効果が目に見えて分かりやすいののですが、保育や遊びだと私たちの関わり方ではすぐに効果がでないことが多いですよね。お母さんやお父さんたちは毎日、お子さんを見ているから気づかない部分もあると思います。ある程度時間が経ち、「この子はこんなことができるようになった」と目にみえる変化や「僕これができるようになった」と本人の気付きは、遊びの中で実感・体感していけるところはあると感じています。デジリハのツールは子どもたちも、大人も、変化に気づかせてくれる特別なツールです。
八尾市立障害者総合福祉センターサイト:https://www.kizuna-yao.org/
instagram:https://www.instagram.com/rainbow_kizuna/
更新日2024年11月22日
記事一覧に戻る